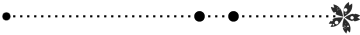【白が舞う日に・・】のその後の話です。
(ここでの名前変換はできません。ご容赦下さい。
名前変換ご希望の方は、バナーよりお入り下さい。)
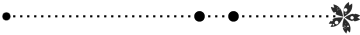
【降り積もる静寂に、足跡。】
「まさかこんなに大盤振る舞いになるとはね〜。」
見上げた先には、綿のような雪が途切れることなく柔らかにふわふわと空を漂っている。
自隊の隊長の誕生日に、と贈ったはずの雪がまさかここまで本格的に降ってくるとは。
不意に、目に映る景色の中で雪の白が揺れると
冷たい風が吹きつけてきて、じわじわと芯まで伝わる冷気に乱菊は体を竦めた。
お酒ですっかり温まっていた体すら、一気に冷え切ってしまいそうだ。
―私も、あの二人には本当に甘いのよね。
店の窓からも牡丹雪が華やかに闇夜を彩っていているのは見えていたし
外の冷え込みも相当なものだろうと分かっていた。
それなのに。
「ありがと。でも、今日はちょっと寄り道する所があるの。」
一緒に飲んでいた京楽と七緒が部屋まで送っていくと申し出てくれたのを
迷うことなく断っていた。
そして、この寒空の下、わざわざ遠回りして十番隊の隊舎を目指しているのだ。
―だって。この雪見てたら、思い出しちゃって放っておけないじゃない。
・・・まさかとは思うけど、
美月がくるのを一人で待ち続けていたりなんて・・してないわよね?
あの子、ちゃんと隊長のところに行ったわよね?
日番谷を残して執務室を飛び出してきた夕刻から、結局気になって仕方ないのだ。
九割方は大丈夫だろうと思うのに、それでも足は雪道を進んでいく。
過保護だという自覚もあるし、お節介だというのも分かっている。
だけど。あの二人はあまりにも純粋すぎて目が離せない。
―それに・・嬉しかったのよ。
あんなに素直で不器用な隊長が見られるなんて。
あれは確か、美月が執務室に隊長を訪ねて来た日から
少し経った頃だったと思う。
「なあ。・・・例えばの話だ。
朽木に、ああ兄の方な。飯に誘われたら、お前着いてくか?」
日番谷にしては何とも珍しいことに、何気ない風を装っているのが
分かってしまうような切り出し方だった
「まあ、そりゃ勿論。」
「・・なぜだ?」
乱菊は日番谷の質問の意図に何となく検討がついて、微笑ましくて仕方なかった。
―あの子ね。
「だって、断る理由ないですよ。いいお酒奢ってくれそうだし。
それに相手は隊長だし、まあ付き合っといて損はないですね。」
わざと意地悪な答えを返して様子を窺ってみると、
日番谷は眉を寄せて黙り込んでしまった。
「まあ一度ぐらいならいいでしょ。」
「・・なら、二度目は断るのか?」
「さあ、どうでしょうね。でも、何度もってなると流石に考えますかね。
で、隊長はどうなんです?次は何度目のお誘いですか?」
ストレートなその質問にはさすがに動揺したらしく
息を呑んで綺麗な目を大きく見開いてから、一瞬の逡巡の後にふっと大きく息をついた。
・・敵わねえな。とでもいうように。
「あいつ。分からねえ・・」
どうやら、朽木隊長と恋次が大事にしてきた秘蔵っ子を
何度も六番隊から連れ出しているらしいのだが、未だにあの子の気持ちが分からない。
と、そういうことらしい。
女になんざ興味ねえ。って顔してた隊長が
たった一人の女の子にこんな風に思い悩まされる日がくるなんて。
まあ、隊長の口から甘い言葉がすらすらと出てくるなんて想像できないし。
美月も美月で、今まで近づいてきた男たちは気づかないうちに
朽木隊長に抹殺されてたんじゃないかっていうぐらい恋の噂なんてない子だったから。
きっと、お互いどうしていいのか分からないのね。
なんて手がかかる二人。
それなのに、私はあの時から決めていた。
・・だって。嬉しかったのよ。
*
柔らかな雪が時折頬を掠めて、その度にヒヤッとした感触が肌に溶けていく。
窓から見た時には「幻想的」と心踊るようだった白い世界に、
今ではすっかり自分自身が取り込まれてしまった。
―本当なら、今頃はもう湯船に浸かって冷えた体を温めている頃なのに。
誰に頼まれたわけでもないが、やはり少しはこの苦労をあの二人に知ってもらっても
いいんじゃないかと思う。
もしも、隊長が一人寂しく執務室に残っていたとしたら
その時にはもう一杯飲みに行って奢ってもらうんだから。
・・きっと凄く機嫌悪いだろうけど。
門を警護していた隊士たちに声をかけて
もう誰も残ってはいない隊舎に足を踏み入れる。
徐々に近づいてきた目的の場所に視線を遣ると、
執務室の辺りがぼんやりと明るい。
・・ああ。これは、隊長も大荒れかしらね。様子見に来て正解だったかも。
隊舎の中は地面に降り注ぐ雪の音さえも聞こえてきそうな
特有の静けさに包まれているような気がした。
その静けさは執務室の中も同じで、乱菊は扉の前まで辿り着いたものの
扉の下からわずかに漏れ出す光の前で、その扉を開くのを一瞬躊躇った。
日番谷が灯りを消し忘れて帰るということは考え難い、
となるとまだ部屋にいるはすなのだが気配がない。
もともと日番谷は常から完璧なまでに霊圧を消してはいるが
中は静か過ぎる。
改まってノックしてっていうのも変だし・・
ここは執務室なんだから気を遣う必要なんてないわよね?
乱菊はそう決め込むと、中に声をかけた。
「隊長?いますか?」
返ってこない返事。
そろそろと扉を開けると、
上司が陣取っているはずの机にその姿はなく、
その代わりに夕刻には散らかっていた書類たちが
きっちりと机の上に積み上げられていた。
足を踏み入れると、次に目に飛び込んできたのは
その手前。
来客用に設置されているソファの上に体を横たえている人物だった。
隊主羽織のない死覇装の黒。しかし、髪の色からしても日番谷であることは間違いない。
―もしかして。待ちくたびれて眠っちゃったとか?
そっとソファに近づいてから、こちらに背を向けて眠る上司に
―風邪ひきますよ?
と声をかけようとして、乱菊は慌てて言葉を飲み込んだ。
先までは陰に隠れて見えなかったが、そこにはもう一人の黒髪の少女。
白い羽織に包まれて、そのまま日番谷の腕の中にしっかりと納められていた。
抱き寄せた腕の中に天使。の図といったところだろうか。
―なんだ。ちゃんと来てたのね。
二人の表情は見えないが、きっとこの上なく穏やかで幸せに違いない。
―もう私が手を貸す必要なんてないのかもしれないわね・・
そのままぼんやりと二人を見守っていると、
随分前に日番谷が言った言葉をふと思い出した。
「分かるだろ。・・こいつだなって。」
いつだったか、「なんで美月だったんですか?」と問いかけた
乱菊への答えだ。
その時は隊長も見せ付けてくれるじゃないと思ったものだが、
驚いたのはその後。
美月にもからかいついでに同じことを尋ねた時だった。
「理由ですか?うまく言えないですけど。
でも・・分かるじゃないですか。この人なんだなって。」
二人を見ていたら、
運命ってやつを信じたくなる。
だから、今でも目が離せない。
鼻がツーンとするような寂しさと暖かさと。
今日は、やっぱりもう一杯飲みたい気分かもしれない・・