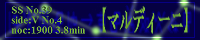□2016年 夏期
2ページ/8ページ
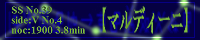
【マルディーニ】
駅前通りの商店街に暖簾を掲げるその大衆食堂は、屋号を「定食のマルディーニ」といった。
和食を中心に洋食、中華の幅広いメニューをリーズナブルな価格設定で取り揃え、店主夫婦の人柄のよさも相俟って地元民から根強い支持を得ている定食屋である。
そんなマルディーニの一角、入口から一番離れた店内最奥の席に向かい合って座るのは、険しい顔をした二人の男であった。片や壮年の、片や十代半ばの少年。互いに筋骨隆々とまではいかないまでも、鍛えられた長身の体躯に仕立てのいいスーツを少し着崩して、考え込むように俯いて腕を組む。会社の上司と若い部下、という雰囲気でもなければ、かと言って親子というわけでもないようだった。
壮年の男がグラスを傾け、氷がからんと小さく音を立てる。雰囲気だけならシックなバーで嗜むバーボンか何かのようだが、勿論ここは定食屋で手にしているのはただのお冷やである。
「さあ、約束の日だ。答えを聞かせてもらおうか」
男の言葉に少年は重々しく息を吐く。
二人は探偵であった。そして壮年の男は少年の師ともいえる立場にあった。そんな師が今から一週間前、少年に課したのは他でもないこの「マルディーニ」の調査だった。
なぜ師はマルディーニを探らせたのか。
その理由さえも自ら解き明かしてみせよとばかり、師は多くを語らなかった。
少年は、師を一瞥してから語り出す。
ここマルディーニではイタリア料理も提供されている。壁に掛けられた遠近法でピサの斜塔を支えているような写真も、一見すると単なる海外旅行ではしゃいでいる記念写真だが、あるいは本場イタリアでの修行時代の写真なのかもしれない。イタリアの人名であるマルディーニを店名に選んだのは、その辺りが理由だろうか。
しかし、メニューは国を問わず多岐に亘り、そのどれも一般家庭で食されるようなものばかり。イタリア料理もその一つでしかなく、店名の割には殊更それを推すような様子もない。
客層もこれと言って特徴はなく、見知った周辺住民ばかり。20〜30代以上のお一人様が多いようだが、定食屋に単身者がやってくることに不自然さなど何もない。
そこまで語り、少年は唇を噛む。
いくら調べようともわかることは、ここが何の変哲もない定食屋であるということだけだった。
どうして店名が「マルディーニ」である理由など探らせたのか。この店には一体なにがあるというのか。
師の思惑がわからない。そんな自分の無力がなにより悔しい。
肩を落とす少年に、師はとんと額を小突いて小さく笑う。その顔に落胆や同情の色は見て取れなかった。
「ま、そんなもんだろう。いや、よくやったな」
「おやっさん……」
「気にするな。十分だ」
「で、でも……!」
期待に応えられなかったのだと、そう悔しがる。そんな少年の肩を、不意にぽんと叩いたのは一人の女性だった。
「ふふ、そうよ。どうせ単なる暇潰しですもの」
「え?」
言われて振り向けばそこには定食屋に似つかわしくない紺のスーツにブロンドの……いや、似つかわしくないどころか怪しすぎる銀の仮面の女が微笑を浮かべて佇んでいた。なんなら通報されてもおかしくない出で立ちであったが――
「あ、餃子2人前と炒飯大盛りでいただけるかしら?」
「あいよー」
なんて当たり前のように注文し、店主も当たり前のように応える。突っ込み所は沢山あったが、いや、今はそんなことよりも、
「おい、おやっさん。暇潰しってどういうことだ」
問えば壮年の男は一瞬顔を背けてから少年に向き直り、真摯な表情で言う。
「探偵としての素養を磨く為の訓練だ」
「なんて言いつつ依頼がなくて暇を持て余していただけでしょう。うふふ」
仮面の女の言葉にも壮年の男が表情を崩すことはなかった。なかったが、なぜか「ぎくり」というオノマトペが聞こえた気がした。
男たちは黙り込む。そんな時、沈黙を裂いて割って入るのは店員の女性だった。
「はーい、餃子と炒飯お待ちー」
「あら、ありがとう。ねえ、ところでお店の名前にはどういう意味があるのかしら?」
「ん? ああ、マルディーニはおじいちゃんが……あ、二ノ丸次郎っていうんだけどね、自分の名前をもじって付けたらしいよ」
「ふうん。……だそうよ?」
「ああ……」
言われて男たちはこくりと頷いて、そしてまた押し黙る。
いっそデジモンでも出ないだそうか。そんな悪い考えが頭を過ぎる。
町は今日も平和であり、男たちは、今日もすこぶる暇であったという。
-終-
SS第39弾は【マルディーニ】。
自分で考えといてなんだけど、なんだこのお題。