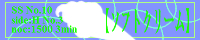□2015年 夏期
4ページ/11ページ
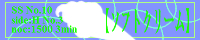
【ソフトクリーム】
ソフトクリームだと、一目見て少女はそう思った。
デジモンの姿形というのは実にバリエーション豊かなもので、聞けば「食物型」なる種族分類まであるという。デジタルワールドのどこかには見た目そのままスイーツなデジモンたちが暮らすスイーツの国もあるそうだ。弱肉強食のデジタルワールドにおいてそれはあまりにもあんまりじゃないかという気もするが、一先ずは置いておこう。
あなたもその国で暮らしていたのかと、尋ねてみればしかし彼は違うと笑う。
成る程確かに、広大なデジタルワールドの中にあってたった一つの国だけに同種のすべてを押し込めておく理由もないだろう。かくいう少女もまた、今暮らしているこの日本という国で生まれ育ったわけではない。デジモンに至ってはそもそも、どこの誰がいつどのような種に進化するかもわからないのだ。
彼と出会ったのはほんの数日前のことだった。桜も散って久しい、太陽が照り付けるそんな夏の始まる頃のこと。遠くデジタルワールドから遥々次元を越えてやって来た彼は、逸れてしまった仲間を探しているのだという。
少女は彼を見て驚いた。いや、勿論誰だって驚きはするだろう。けれど少女が驚いた理由は、大多数の人とは違っていた。
少女はデジモンを知っていた。今は離れ離れになってしまったがパートナーもいた。少女はかつて“選ばれし子供”と呼ばれていた。異世界でたった独り、どこにいるとも知れない仲間を探して彷徨う彼を、放ってはおけなかった。
とはいえ今の少女にできることは、彼がこの近辺にいる間、食事と寝床を提供するくらいのことだけだったのだが。申し訳なさげな少女に彼は、感謝してもしきれない程のことをしてもらっていると礼を言った。
二人が一緒に過ごしたのは僅か一週間ばかりのことだったけれど、二人の間には確かな絆があった。友情を育んだ。
二人でご飯を食べた。お喋りをした。意味もなく河川敷を自転車でかっ飛ばした。トランプじゃ何をやっても彼には負けてばかりだった。父の日のプレゼント選びになんかも付き合ってもらった。たまにちょっとだけ喧嘩もした。それから、仲直りをした。
二人は、友達だった。
どうやらこの付近にはいないようだと、拠点を移すべく彼が少女の元を去る時、二人の目には涙が浮かんでいた。
彼はお別れの間際、言い辛そうに何かを伝えようとしていた。しかし少女は人差し指をそっと口元に当て、その言葉を遮るのだ。
今度会ったら教えて。
そう言って少女が微笑むと彼もまた笑う。
また会えたらきっと伝えよう。いつか言いそびれたことを伝えよう。そう心に誓って、彼は再び当て所ない旅に出る。
ともすると、伝える必要などないことだったのかもしれないけれど。
デジモンに多様な種族があるように、人間もまた多くの異なる民族によって成り立っている。肌の色、髪の色、目の色が違えば、思考、思想、信仰も違う。文化が違えば認識も違う。同じものを見たとしても、まったく別のものを認識してしまうことさえあるのだ。
礼を一つ挙げるなら――欧米人の多くがソフトクリームだと認識するその形は、日本人から見るならうんこ以外の何物でもないわけである。
うんこ型デジモン・ダメモンは、にこやかに見送る金髪碧眼の少女に手を振って、茜色に染まる夕方の河原をどこか軽やかな足取りで歩いていく。デジタル空間でついうっかり落っことしてきたチューチューモンが今一体どこにいるのかは、まだわからない。
それはともかくとしてその日の夕焼けは、なんだかとっても綺麗だった。
-終-
第10弾は募集お題【ソフトクリーム】です。
一言で言うならうんこの話。ソフトクリームなど影も形もないうんこの話です。ひどいよね。