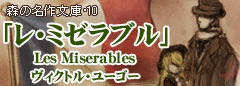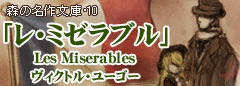□第四部 叙情詩と叙事詩 プリューメ街の恋歌とサン・ドゥニ街の戦歌
6ページ/471ページ
シャール十世はシェルブールへの旅行中、丸いテーブルを四角に切らした、そして崩壊しかけた王政よりも乱れかけた儀礼の方にいっそう心を痛めてるらしかった。かかる低落は、ブールボン家の者を愛する忠誠な人々を悲しましめ、その家がらをとうとぶまじめな人々を悲しました。しかるに民衆の方はいかにもみごとであった。
ある朝、武装した王党の暴動とも言うべきものに国民は襲われた、しかし国民は自ら力あることを感じて、別に憤りもしなかった。
国民はそれを防ぎ、自らおさえて、事物をその本来の場所に、すなわち政府を法律のうちに戻しブールボン家を悲しくも追放のうちに戻し、そしてそれでやめた。ルイ十四世が身を置いた天蓋の下から老王シャール十世を取り出し、それを静かに地に置いた。
王家の人々に手を触るることを、国民はただ悲しみと用心とをもってしたのである。
防障の役(一五八八年五月)の後ギーヨーム・デュ・ヴェールが発した荘重な言葉を、今更に思い起こさしめ、全世界の眼前に実行したものは、それはひとりの者ではなく、また数人の者ではなく、実にフランス自身であり、フランス全体であり、勝利を得、自らその勝利に酔ったるフランスであった。
ギーヨームの言葉に曰く、「貴顕の愛顧を求むるになれ枝より枝へと飛び移る小鳥のごとくに、悲運より幸運へと向背するになれたる者どもにとりては、逆境にある君主に対して不敵なる態度を取るはいとやすきことなり。さあれ吾人にとりては、わが王の運命は常に尊重すべく、いわんや悲境にある王の運命をや。」
ブールボン家は尊敬をにない去った、しかし愛惜をにない去りはしなかった。
前に述べたとおり、彼らの不幸は彼らよりもいっそう大であった。
彼らは地平の彼方に消えうせてしまった。
七月革命は直ちに、全世界に味方と敵とを得た。
味方は心酔と歓喜とをもってその方へ押し寄せ、敵は各その性質に従ってそれに背を向けた。
ヨーロッパの諸君主は、まず初めに、その曙における梟のごとくに、おびえ驚いて目を閉じた、そして再びその眼を開いたのはただ威嚇せんがためのみであった。
それは道理ある恐怖であり、宥恕すべき憤怒である。
この不思議なる革命はほとんど突撃の手を振るわなかった。
敗亡したる王位に、敵対して血を流すだけの名誉をさえ与えなかった。
自由が身自らそこなわんことを常に喜ぶ専制政府の目から見れば、恐るべきものでありながら、しかも静かに手を拱いてるということが七月革命の錯誤であった。
その上、七月革命に対抗して試みられ計画されたところのものは何もなかった。
最も不満なる者、最もいら立てる者、最も戦慄を覚えてる者でさえ、皆それに対して頭を下げたのである。
人の利己心と怨恨とがいかに強かろうとも、人間以上の高き手が共に働いてるのを感ぜらるる事件に対しては、ある神秘なる敬意が生ずるものである。