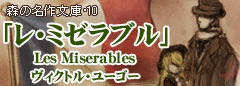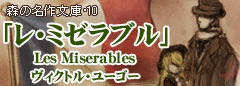□第四部 叙情詩と叙事詩 プリューメ街の恋歌とサン・ドゥニ街の戦歌
5ページ/471ページ
また国民は平和の偉大さに親しむに至った、そしてそれはまさしく帝政時代に欠けていたものである。
自由にして強大なるフランスはヨーロッパの各民衆に対しては心強い光景であった。
ロベスピエールの下にあっては革命が口をきき、ボナパルトの下にあっては大砲が口をきいていた。
しかるにルイ十八世およびシャール十世の下においては知力が口をきく順番となった。
もはや風はやんで、炬火は再びともされた。
清朗なる高峰の上には純なる精神の光明がひらめくのが見られた。
それこそ壮大なる有益なるかつ魅力ある光景であった。
十五年の間、平和のうちに、戸外の巷に、偉大なる主義が働くのが見られた。
それらの主義は、思想家にとってはいかにも陳腐であったが、為政家にとってはいかにも斬新であった。
すなわち、法律の前における平等、信仰の自由、言論の自由、印刷出版の自由、人材に対して職業の開放。
そういう状態は一八三〇年まで続いた。
ブールボン家は文明の一道具であって、ついに神の手のうちに握りつぶされたまでである。
ブールボン家の没落は、彼らの方ではなく国民の方において、壮観をきわめた。
彼らは粛然としかし何らの権威もなく王位を去った。
彼らの滅落は、史上に陰惨なる感動を残す壮大な消滅の一つではなかった。
シャール一世の幽鬼のごとき静穏でもなく、ナポレオンの鷲の叫びでもなかった。
ブールボン家はただ立ち去った、それだけのことである。
彼らは王冠をそこに置いた、そして自ら円光を保有しもしなかった。
彼らはりっぱであった、しかしおごそかではなかった。
彼らにはある程度まで不幸の壮大さが欠けていた。