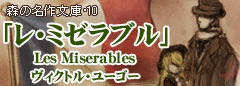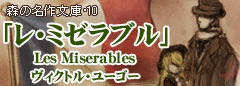□第四部 叙情詩と叙事詩 プリューメ街の恋歌とサン・ドゥニ街の戦歌
4ページ/471ページ
ブールボン家なくとも事は足りた。
実に二十二年間はブールボン家なくして済まされたのである。
そこに連続は中断されていた。
しかしブールボン家はそれを毫も知らなかった。
実際、ルイ十七世はなお共和熱月九日(一七九四年七月二十七日)にも君臨しルイ十八世はマレンゴーの戦いの日にも君臨していたのであると想像したブールボン家は、いかにしてそれを知る術があったであろうか。
有史以来かつて、事実の現前に対して、事実が含有し公布する神聖なる権力の配当の現前に対して、かくまで盲目なる君主は存しなかった。
かつて、国君の権利と称せらるる地上の主張によって、かくまで天上の権利が拒まれたことはなかった。
ブールボン家をして、一八一四年に「欽定された」保証の上に、彼らのいわゆる譲与の上に、再び手をつけしむるに至ったことは、いかに重大な誤謬であったか。
痛むべきかな、彼らが譲与と名づけたところのものは、実は吾人のなした征服であり、彼らが吾人の簒奪と呼んだところのものは、実は吾人の権利だったのである。
復古政府は、時期至ったと思われた時に、ボナパルトに打ち勝ち国内に根をおろしたと想像して、換言すれば自らを強固なる根深きものと信じて、にわかに決心の臍を固めてあえて事を行なわんとした。
ある朝彼はフランスの面前につっ立ち声を張り上げて、その集団的資格と個人の資格とを否認し、国民には大権を拒み公民には自由を拒んだ。
他の言葉をもって言えば、国民に対してはよってもって国民たるべきものを否認し、公民に対してはよってもって公民たるべきものを否認した。
七月の勅令(一八三〇年)と称せらるるあの有名なる法令の根本は、実にそこにあったのである。
かくて復古政府は没落した。
その没落は至当であった。
しかしながらあえて言わんに、復古政府とてあらゆる進歩の形式に絶対的敵意を有するものではなかった。
すなわちそのかたわらにおいてある大事業もなされたのである。
復古政府の下において、国民は静穏なる談論に親しむに至った、そしてそれはまさしく共和時代に欠けていたものである。