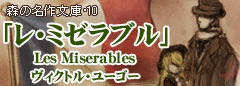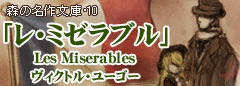□第四部 叙情詩と叙事詩 プリューメ街の恋歌とサン・ドゥニ街の戦歌
3ページ/471ページ
しかしこの真理を一六六〇年にスチェアート家は寸毫だも知らず、一八一四年にブールボン家は念頭に浮かべだにしなかった。
ナポレオンが覆滅した時フランスに帰ってきた宿命的なブールボン家は、嘆くべき単純な考えをしか持っていなかった。
すなわち、与うる者は自分である、そして自分が与えた所のものはこれを再び取り戻すことを得ると。
ブールボン家は神法を持っている、しかしフランスは何物をも持たない。
ルイ十八世の憲法の中で国民に譲り与えた政治上の法律は、神法の一分枝に過ぎなくて、ブールボン家自らそれを折り取って、王が再び手にせんと欲する日まで人民に許し与えたものであると。
しかしながら、人民へのその贈り物は実はブールボン家から贈ったものでないということを、それがたとい不快であろうともブールボン家自身感ずべきはずだったのである。
ブールボン家は十九世紀には至って神経質であった。
そして国民が翼をひろげるごとに悪い顔つきをした、平凡なる、すなわち通俗で真実なる言葉を使えば、渋面を作った。
民衆はそれを見たのである。
ブールボン家は、自分の前に帝政が劇場の大道具のごとく運び去られてしまったゆえに、自ら力を持っているものと信じた。
しかし、ブールボン家自身も同じようにして持ちきたされたものであることに気づかなかった。
自分もまたナポレオンを奪い去った同じ手の中にあることを知らなかった。
ブールボン家は、自分は過去であるゆえに確固たる根を持っていると信じた。
しかしそれは誤解であった。
ブールボン家は過去の一部分のみであって、全過去はフランス自身であった。
フランス社会の根はブールボン家の中にはなくて、国民のうちにあった。
その人知れぬ頑丈なる根は、一王家の権利を組織するものではなくて、一民衆の歴史を組み立てるものであった。
その根は至る所にあって、ただ国王の座の下にのみ欠けていたのである。
ブールボン家は、フランスにとってはその歴史の血にまみれたる顕著なる結び目であった。
しかしもはや、その運命の主要なる要素ではなく、その政治の必要なる柱石ではなかった。